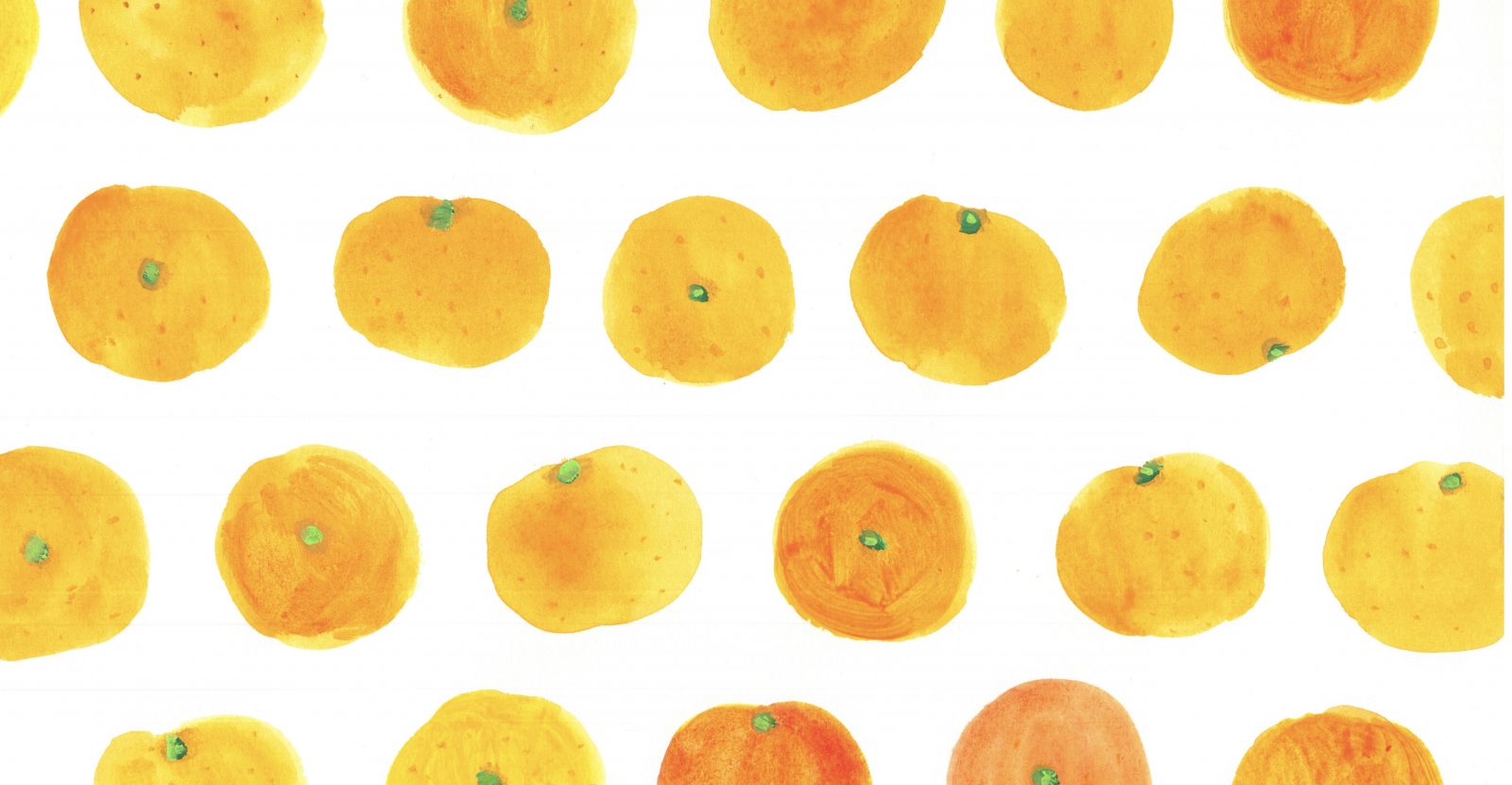イタリア生活で見つける「びとくらし」
イタリアでの日常生活の中にある、すこしだけ幸せに感じたり、すこしだけリラックスできたりするような「びとくらし」的な出来事を、マルケ州アンコーナ住まいのライターが紹介します。
イタリアに暮らす彼女の話しを聞いていると、度々、イタリアでは日本と全く違う時間が流れているように感じることがあります。しかもとても豊かな時間でした。時間の流れの違いの中に豊かさの理由が隠されているように思えてなりません。ぜひ、この理由を一緒に探してみませんか?
車社会のイタリアでの生活
みなさんはマイカーをお持ちでしょうか?
日本では若い世代を中心に車の所有が減っていると言われています。経済的に厳しくなってきている事実は否めませんが、なんと言っても公共交通機関の充実ぶり、その運行の正確さがあってこそのマイカー離れなのでは無いかと思います。
イタリアで、一般的な中流家庭で一台も車を所有していないという世帯は存在するのでしょうか。たとえどれだけ都会に住んでいたとしても、自家用車は所有している様な感覚があります。私が住む都市部ではないけど、田舎でもない住宅地住まいとなると、車以外の移動は基本的にバスが中心となります。イタリアの国鉄であるトレニイタリアも走ってはいますが本数が少なく、駅自体が街の外れにあることも多く、簡単に移動ができるわけではありません。
また、ローマやミラノなどの都市部に住んでいたとしも、市内はバスや地下鉄などの公共交通機関で移動が簡単にできますが、一度、都市部から外れた場所に移動するとなると車無しでの移動が難しくなるため、マイカーを保有しがちになるのではないかと思われます。また、無料で高速走行ができるフリーウェイが多く存在し、有料道路に関してもその料金が電車の切符料金と比較して割安なことも理由に成るのかも知れません。
ともかく、マイカーはイタリア生活では切っても切れないものであって、私もこちらに来て2年目にはマイカーを所有し、通勤はもちろん、買い物やお友達のお宅訪問などには必ず使っていました。
そんなイタリア生活の命綱とも言えるような私の車が2021年を目前にダウン。
レッカー車で車屋さんまで運び状況を確認してもらうもダメージはひどく、結局買い替えることになり、先にも書いたように出かける時は車移動が常だった私の生活が、2021年からはガラリと変わり、移動はバス利用が中心となったのです。
なぜか不便、なにが不便?
夫婦二人の生活で、それぞれがマイカーを所有しています。ですので、私に車が無くなったとしても週末は夫の運転でどこにでも連れて行ってもらえるので、日用品の買い出しは週末にまとめてすることで一旦問題は解決。
ちなみに、イタリアの車はミッション車が殆どをしめており、夫の車もミッション仕様。オートマチック車の運転に慣れている私は運転を拒否している次第です。
一番の問題は毎日の通勤。
市街地ではなく街の外れにある商業地域にオフィスがあるので、自動車を除いた移動手段はバスとなり、しかも、乗り継ぎが必要になります。自動車での通勤ならば、山を突っ切る形で走るフリーウェイを利用して15分少々で到着する道のりが、バス利用だと大きな街を経由して谷地をぐるりと回っていく行くために1時間もかかるようになりました。
日本でも恐らく都市部を離れると同じ様な状況になるのでしょう。
ですが、こちらのバス事情は心做しか少し複雑に感じてしまいます。
恐らく、バス停が半分壊れているような状態でわかりにくい、時刻表などが掲示されていない、時間通りに運行されない(時間よりも早く来ることもよくあります)、バスの運転手が乗客とずっとおしゃべりしている、などの難点が重なることによって、日本のバスよりも不便だと感じてしまうのかも知れません。
実際、仕事場までバスを初めて使う日の前日は、インターネットを検索したり実際にバス停に行ってみたり、地図を開いたりとその準備に大忙し。
色々な人に聞いたところで、恐らく彼らが信じている「正しいであろう」答えを与えてくれるだけで、「正しい答え」なわけではなく、とにかく自分で調べることが一番正確で早道なのです。
料金の支払いもバス内で完結させることはできず、事前にチケットを購入しておく必要があります。しかも、移動距離で値段が変わるので、一体自分の移動距離がどれだけあるのかを把握しておく必要があり、その売り場の開店時間を把握しておく必要もあります。というのも多くのお店はランチタイムは数時間クローズしますから。
慣れてしまえばどうってことないことなのですが、バスを使う人が圧倒的に少ない環境なので何事もスムーズにいきません。
だからバスを使う人が増えないのかも知れませんね。
ちょっとした冒険気分の毎日
さて、私のバス通勤が始まりました。
とにかく歩いている人が少なく、歩道が確保されていない場合が多いので、バス停にたどり着くまでは注意が必要です。交通量の多い車道を横切るのも、信号の無い横断歩道ですので、右左右左右と確認し、子供のように挙手して渡ります。
そしてバスに乗ると気がつくことが一つあります。
それは乗客の殆どが異国の人たちであること。
肌の色、目の色、髪の色がみな違い、服装も違えば飛び交う言葉も様々です。
この国ではバスは「車を持たない人」が使う交通手段ですので、自ずと所得が低い人たちの使う機会が多くなります。所得が低い人といえば、イタリアでは各国からの移民者があげられます。
移民というと、アフリカがまっさきに思い浮かぶと思いますが、アジアや中東エリア、東欧エリア、南米と実に様々な国からこの国にやって来ます。
そこに日本人である私も混じってまさに人種の坩堝状態。
彼らの繰り出す会話の音にまじわりながら、空の青さを木々の様子を確認したり乗客たちの表情を盗み見して約1時間にわたるバスの旅を遂行するわけですが、これがなかなか心地よいのです。
自分で車を運転してオフィスまで向かう場合は、とにかく運転に集中し、他の考え事はしないようにしていましたが、バスでの移動となるとそんな必要もなく、移動時間は私が自分のために使える時間になりました。
日本を離れてから、とんと本を読まなくなったのですがが、それは通勤時間や電車での移動時間が無くなったからだと気づきました。
バス通勤になって、ようやくあの「自分のための豊かな時間」を手に入れたことを実感し、これもこれで悪くないかも、なんて調子よく感じられている自分を不思議に感じますし、こうやって人間はいろいろなことに折り合いをつけて受け入れていくのだなぁ、と実感しました。
イタリアの都市部から我が家の近所に引っ越してきた、車を持たない日本人の知り合いとの会話で「ここはとにかくバスが不便で困るよね」と言っているのを聞いたのですが、思わず「いやいや案外便利だよ」なんて言い出しそうな自分がいて、おかしくなった今日このごろです。